うゆです。
1回だけパーでチョキに勝ったことがあります。
1つ前のブログに『海辺の墓地』の引用が出てきたので、こちらもぜひ読んでくれたら嬉しいなと思って載せました。自分でもよく書けたと思っているし、評価も満点でした。レポート自体がひとつの建築のようになって、最後の最後に軽やかに浮び上がる構成です。
ここには著作権の関係でもとの詩を載せることができないのですが、調べれば出てくるので、読んだことのない方は比べながら読んでみてください。
真昼の交叉穹窿:『海辺の墓地』の建築的構造
Newtype 1年2組 うゆ
本論の目的は、ポール・ヴァレリーの詩「海辺の墓地」(Le cimetière marin, 1920)を題材として、ヴァレリーの建築や時間に関する考え方をもとに本作の構成を分析することである。特に、厳密に設定された全体の対称性をゴシック建築における交叉穹窿/ヴォールトに見立て、停滞から運動、再び停滞に至る波のような円環構造や、生と死、運動と停滞、永遠と一瞬、精神と肉体といった対立構造を論じていく。なお、筆者のフランス語技能の不足のため、分析には中井久夫による翻訳を基本とし、併せて鈴木信太郎訳(『ヴァレリー全集1:詩集』筑摩書房)、菱山修三の散文訳(『海辺の墓』椎の木社)を適宜参考に用いた。従って、原文に見られる押韻を中心とした分析は不十分なものとなった。
「海辺の墓地」は、1行10音綴、1節6行、全24節からなる詩である。フランス文学者の長谷川が「詩の言語はそれ自体、完成した一つの世界を作るのであって、現実の世界を模倣しない建築芸術と自立性の点に於て一致している」[1]と指摘するようなヴァレリー流の厳密な設計に基づいて作られており、1行を一般的な12音ではなく10音綴とし、さらにその10音を前半4、後半6音綴に分割する詩型が語に先立って決定された。最終稿ではおおよそ1、3、8、13、14、15、21、24節にあたる7節からなる基本的な構想が提出された後、それぞれ10節、18節、23節で構成された改訂稿が書かれ、1920年に書かれた24節のプレオリジナル版に並べ替えといくつかの改訂を施した形で、同年に決定稿が「切断」[2]、つまり完成ではなくヴァレリーに言わせれば暫定的な決定の形で発表された。本詩における構造への厳密な定義について、ヴァレリーは
この心組みのおかげで、私は、ある自我の瞑想を詩的世界に移して示唆するために、自分の作品が含むべき感覚的なもの、感情的なもの、抽象的なものを、かなり容易にそこに配置することができたのである。[3]
と明らかにしており、この詩にとって、構造というものが単なる一つの拵えものとしてのこだわりではなく、詩が詩としてあるために必然的な身体としてあったことがわかる。ほとんど全ての語が直接法、命令法で書かれたこの詩の印象として、中井が詩人自身も明らかにしているダンテの影響を引き合いに出しながら「硬質な明晰性」[4]とまとめている一方で、描写される海がヴァレリーの生まれ故郷であるフランスの港町Sète[5]から臨まれたものであることを考えると、実際には詩型や文法的要素から受ける印象とは裏腹な、ごく個人的な記憶が詩の全体を駆け巡っているということができる。それはいわば逆方向の受肉の結果である。すなわち、先立ってある貝殻の内部に貝自身の身体が後から受肉されていくように、確固として構成された形式の中に詩の血肉としての語が稠密に配置されていくことで、構造の内部には静かな運動が張り詰めているのである。なお、これは例えば詩作において同じように建築的構造を重視したロシアのアクメイズムとは異なる方法に基づいている。アクメイズムが言葉を多層的に結ばれあった意味の集積体である石材として扱い、それらを地表から積み上げていった先の建造物として詩を捉えたのに対し、ヴァレリーはあらかじめ建造物の全景を概観し、それを可能にする構造を完全に定めた上で、その輪郭を最も美しく実現しうる素材として言葉を探していったのである。そして、「海辺の墓地」においてヴァレリーが目指した建造物こそ、ゴシック建築に見られる交叉穹窿/ヴォールトの形であった。これはヴィオレ=ル=デュクが指摘するところの、構成物の全てを構造の機能としてみなしうるゴシック建築の屋台骨をなす特徴である。[6]穹窿同士を肋骨/リヴで補強することによって、推力に対抗しうる圧力が緊密に形作られた穹窿の静止、均衡状態と少数の柱の中のみに発生するようになるため、旧来のロマネスク建築で問題点とされた重厚な壁面を大幅に軽量化することができるようになった。この構造はまさしく停滞と運動の均衡状態であり、静かで硬質な殻の中に運動する身体を閉じ込めた貝さながら、厳密な構造と鮮やかな生への運動とが均衡した「海辺の墓地」という詩を象徴するものであると言えるだろう。
「海辺の墓地」の全体を貫く構造を捉えるテーマとして、長谷川は、詩人と絶対的な外部世界の交歓としての“absolu/絶対性”、地上的なものとして実感される生である“vie /生”、そしてそれに忍び寄り、地中であらゆるものを融解させる死である“mort/死”の3点を軸とし、天、地、地底に結ばれる縦方向の関係性を詩の構造の中に見出している。以下、長谷川の論文を参考に、本詩の構造を分析していく。[7]
まず、第1節から第4節にかけて、墓地を歩く詩人の目は先に広がる海へ向けられている。冒頭の2行「鳩歩む、この静かな屋根は/松と墓の間に脈打って」における「屋根」は墓地の隙間から臨む穏やかな波の連なりを、「鳩歩む」はその上を揺蕩う船の白い煌めきを表している。波形については、中井がセットの地形を斟酌しながら
かういふ遠浅の海では、平行して岸辺に近づく波の列がみられるだらう(第XXII節第一行参照)。波は砂嘴にはそのまま寄せて引くが、セット岬の正面にくる波はそれより先に岬に打ち上げ、引く途中で次に来る波と衝突して著しい飛沫を上げるだらう。[8]
と分析しており、ここでヴァレリーによって生き生きと描写される海面の光景に、屋根瓦のように整然と並んだ波線と、その局所的な崩壊とが想定されていることが分かる。この場面の随所には「沈黙」、「平和」、「不動の宝」、「静けさの重み」といった停滞状態を暗示する語句が散りばめられており、ここにおける詩人の思索が、晴れた日の真昼の海の如く、静謐で輝きに満ちたものであることが伺えるだろう。そして思索の内的な永遠の中であらゆるものは光の中に停滞し、詩人は過去、現在、未来の収斂する[9]絶対の世界へと誘われる。第1節から第4節における内面の移行について、長谷川は
第1詩節より順次高まる詩の動きは、第4節において頂点に達する。不安定な現時の世界から抜け出、絶対の世界と交感する詩人と云う意味で、仮にこの四詩節をabsoluと名づける。[10]
と定義したうえで、第5節に至って一度地上の「生」に立ち戻る詩人の動きを捉えている。ここで第4節の最終2行、「晴れわたる光は、空の高みに/王者の蔑みを撒き散らす」という詩句を参照し、恍惚に高まりきった詩人の視線が太陽の圧倒的な視線を受けてあえなく撃墜していることを確かめれば、絶対性との交歓がその境地に至って途切れ、詩人の意識が現実的なものへと転換していることが分かる。第5節では、上に触れた太陽の侮蔑を受けて、詩人は「私の未来における火葬の煙を先取りして味わ」[11]うことになる。「息」、「口」、「吸ひ」。呼吸によって世界と結ばれる確かな身体感覚によって、詩人の意識は明敏に研ぎ澄まされ、彼は飛翔の準備を整える。そして第6節、詩人は改めて太陽に挑戦する。頭上に頂く空へ自らの変化を呼びかけ、自らの内奥に充満した力の高まりを確かめながら飛翔する詩人。鳥瞰する下方に死の象徴たる墓地を見遣り、しかしそこに落ち、馴染む影は生を謳歌する自分自身の写し身である。第5節で予感した死の影は、天上をゆく詩人に気配として依然付き纏っているのだ。第7、8節、全てが隈なく照らされた風景の中で、詩人自身だけが唯一の影となる。
「生」の持つ暗い影が詩人をとらえ、彼は自分の内部にこれを問いかける。これ等第5、6、7、8節を、時の偶発性にさらされた自己を意識する詩人と云う意味で、vieと名づける。[12]
ここから第8節の5行、「地下の塩井戸」によって暗示される頭蓋骨を転換点として、詩は死の醸造される地下の暗がりへと移行する。第9節から第12節にかけて、「囚はれ女」、「雌犬」に準えられた海への呼びかけの形をとって、詩人の意識は墓地に充ちる静謐の神秘に耽溺する。「ここはいい。焔の領する所」「遠ざけよ、賢しらの鳩を、/虚しい夢、知りたがりやの天使を!」という詩句からは、詩人が生あるものを積極的に遠ざけ、それらからは隔絶されてある静寂と物質の融解の中に身を潜めようとする意思を読み取ることができる。続く第13、14節では、ここまでに登場した“absolu”、“vie”、“mort”の3要素が対比される。
まず13詩節は、前節に続き美しい墓地の安らかな死者が、続いて死者との対比によって、天井の「絶対」の昼が、最後にこの絶対に対して変化にすぎぬ「生」が歌われる。第14節に於ても、絶対者に対する「生」の相対者の歎きが続く。[13]
ここにおける生は第6節などに見られる積極的で自信に満ちた生の形とは異なっている。「土」、「『真昼』は高き彼方」といった言葉は、詩人の生は太陽に同一視される上昇の階梯ではなく、むしろそれ自体で完結する太陽を遥か上空に見据え、その激烈な光に被曝したまま、地中の死と同化していこうとする下降であることを示している。そして続く第14節で、詩人の思考はさらに死者たちの沈黙へと潜航していく。フランス文学者の天野は、この詩の全体の運動を支配する移行と停滞の対立について論じる中で、本節において停滞の永遠性を見出している。
墓地の永遠は、死の永遠であり、それは、それぞれの生の運動の完遂による静止状態である。これに対し、正中の太陽の静止状態は、充溢する生の力の極限状態における瞬間の永遠性であり、死者たちの永遠とは異なり、生の只中における時空そのものの静止状態、永遠性である。[14]
太陽、詩人、死者。この3点が縦方向の直線で結ばれ、下方へ向かう垂直の圧力が詩の中心を貫くことでアーチの構造を支える静的な運動となる。最大まで引き絞られた弓が刹那完全な沈黙をもって射手の身体と連動するように、運動と停止はそれぞれの極限において完全に拮抗し、その沈黙した内部に爆発的な運動を宿す。交叉穹窿のアーチはここに極まり、詩はこの第13、14節を折り返し地点として対称構造を形作っていく。無論、これは太陽が昇って落ちる黄道の軌跡と重なるイメージでもあり、「海辺の墓地」における本節はまさに太陽がその頂点に正中する真昼の位置に当たるといえる。
第15節から19節にかけて、先ほどとは一転して地中の死者に視線を送る詩人の言葉は、過去における高名な詩人たちの模作へと向かっていく。つまり長谷川の定義を借りれば“mort”にあたる。中井はダニエル・オステールの分析を引用しつつ、この場面の模作の特徴について、それぞれ第15節をラマルティーヌ風、第16節をヴェルレーヌ、あるいはランボー風、17節をロンサール、18節をユーゴー、そして19節をシェイクスピアの『ハムレット』あるいはボードレール風であるとまとめている。[15]実際の語句を参照すると、「溶ける」「虫」「投げ入れた土の重み」といった表現が散りばめられていることから、例えば『カラマーゾフの兄弟』においてゾシマの遺体に「不謹慎な、愚かしい、悪意に満ちた事態」[16]を生じさせたのと同じような、極めて肉体的で忌まわしい、単なるものの腐敗と融解という現象としての死が捉えられていると考えられる。詩人は、模作という形で過去の死者たちと一体になり、地中に留まったまま、自らの肉体の終わりをすら予感しているのだ。しかしこの下降は、死体を食むはずの蛆/verが反転して詩/versの生命に齧りついたことで、詩人は再び地中から這い出、生の世界へと立ち戻っていく。第20、21節について、これらを消極的な“vie”の状態として定義した上で、長谷川は
「生」をかむ虫、即ち意識は常に死の影をもって肉身に迫り、身をさいなむこの意識の思考の果ては、動きを、生命を否定し全てを不動化しようとする。[17]
とまとめているが、この表現はティボーデの生と意識にまつわる解釈に共通するだろう。曰く、
精神をあまりにも一貫して行使すれば、生は不可解なものとなり、その光景はばかげたものと見え、もっとも単純な生の行為にさえ人は唖然とするであろう。全世界は砂漠と化すにちがいない。拒絶された一切の対象は、他の砂粒と同じ砂粒になるであろう。それ以上前進すること、思考の極限にまで進むこと、それは自己の剣のきっさきに、一箇の無に等しいもの、つまり不毛と化した最後の小片をもちきたることにほかなるまい。[18]
詩人は意識に捉われる。内面的な思索に溺れ、あらゆる風景を単一の現象に過ぎないものとしてのみ認識するようになる。思考の極限で生は意味という意味を剥ぎ取られ、そのものの姿を曝す。第20節最終行「この生き物(筆者注:精神的な意識のこと)に血を分けて私は生きる!」の一節には、詩人が内面世界の誘因力に身を任せ、動きや変化に充ちた身体世界と決別しようとする意思が見てとれる。そして「震へ、飛び跳ねかつ飛ばぬゼノンの矢!」「大股のアキレスが金縛り!」といった詩句を含む第21節、とうとう全ての動きは停滞する。
『海辺の墓地』でエレアのゼノンとアキレスと亀の影が現れるとき、世界のあらゆる動きは突然麻痺したように凝固し、金色の太陽の光は曇り、意識は形而上学的めまいのうちに無と化する。[19]
もちろんここで配置されるモティーフはゼノンによって提唱された運動にまつわるパラドックスを想起させるものである。有限の時間は、しかし時間を加えるという行為の際限ない微分によって無限へと膨張する。あるいはあるまとまった時間の中で視点から終点までを疾走する矢は、切り出された瞬間においては停止している。これらの「形而上学的めまい」を念頭におけば、この節において、詩人が連続する時間の支配する物質世界の一切を捨象して、一瞬が即ち永遠にすらなる内面的な持続時間に到達しているのだといえる。実際、この詩節において、ヴァレリー自身は
私は、意識の意識が展開させる在ることと知ることとの間の開きを、容赦なく感じさせるある黙想の、持続と鋭さへの叛逆を表現するために、ゼノンの比喩いくつかを転用したのである。[20]
と述べている。なお、時間感覚については、ヴァレリーはベルクソンにかなり共通した考えを提示している。即ち、それは時間を距離のように計量や比較の可能な記号ではなく、過去の経験に基づいた感覚や認識の産物として捉えようとする試みであり、その論点における時間感覚の中では、身体が経験する一瞬と精神が体感しうる永遠とは両立しうるものである。[21]これらの停滞は変化への恐れに起因するものである。ヴァレリーの時間感覚における変化について、伊藤は
予期されていたのと異なる出来事に出会うことは、世界と主体の間の「ずれ」に出会うことである。主体は、不意を打たれた直後、すぐにこのずれに適応することはできない。それは「遅れ」の感覚である。遅れにおいて主体は迷い、混乱し、ためらう。[22]
と述べ、果断なく生起する変化に対応するために脳内で行われる「予期」→「分解」→「修正」のプロセスと、その間の反応として生じる運動の停止について分析している。この考えをもとにすると、第21節における時間の停止は、外界のあらゆる変化の拒絶に連なる、詩人自身の変化に対する拒絶の結果であると捉えることができる。
しかし第22節、風は起こる。詩人は風によって奮い立ち、精神に飲み込まれていた身体感覚を再び取り戻す。消極的なものとしてあった“vie”は、積極的なものへと反転する。あらゆるものが輝きを帯び、再び放縦に運動を始める。「砕け、わが身体、この思ひの輪を!/飲め、我が胸、この風の誕生を!」、詩人は全身に風を受け止め、みなぎる感覚の全てに己が身を奮い立たせる。停滞の揺籠から抜け出し、繰り返し巻き起こる波のような絶え間ない変化に体をぶつけていく。恍惚の絶対者でも、融解する死者でもなく、呼吸する身体をもった詩人自身として。第23節、「絶対の水蛇がおのが青い身体に酔ひ、/燦めく尾を噛み続けてゐる、」の詩行が示すウロボロスの姿は、波において水分子が描くトロコイド曲線のイメージにも重なる。[23]ウロボロス、あるいは波形が示す円環は無限なるものの予感を詩人に示すが、もはや彼は自分を分解し、変化に対応するための再構築を試みる際限のない営みを厭わないのである。そして堀辰雄の小説『風立ちぬ』のエピグラフとしても知られる1行「風が起こる……生きる試みをこそ!」に始まる最終節で、高まりつつあった運動はその頂点を迎える。荒れ狂う海面に波は乱舞し、砕け、躍り上がる飛沫が太陽の粒となって輝く。しかし、そのようにして示される変化の饗宴の最後に至って、詩は再び第1行目と同じ「帆=鳩」、「静かな屋根」の姿を垣間見せる。つまり、生じ、高まり、砕け、そして再び生じる波のように、この詩自体もまた始まりに戻り、以上に示されたような進行をあらためて繰り返すのである。これについて天野は、
そうして、この詩全体が、一つの纏りであると同時に、何度も繰り返して始めに送り返す、反復運動を蔵した「移行性」の詩でもあるのである。屋根のごとき静の海から、波の逆巻く動の海へ、そしてまた動の海から静の海へ。海が内に蔵しつつ外に向かって映し出す、この永遠の反復性は、この詩全体の基本構造をなす企みといえよう。[24]
と分析し、第13節に見られる「停止の永遠」と対比させる形で、詩の全体を駆け巡る「移行性の永遠」を読み取っている。天野が論じるこの2種類の永遠とは、まさに停止と運動、交叉穹窿の構造を成立させる張り詰めた均衡状態であろう。このような再帰への予感を読み手に託して、「海辺の墓地」という一つの波は見事に砕けるのである。
『海辺の墓地』は第13、14節を頂点とする交叉穹窿を形作る。円環の始点と終点、また海との対峙として、第1-4節のabsoluは第22-24節のvieに対応する。第5-8節にわたる積極的なvieは第19-21節の消極的なvieと、第9-12節の神秘的なmortは第15-18節の肉体的なmortにそれぞれ対応する。[25]詩の全体を象徴するアーチ構造を太陽の黄道に準えるならば、真昼の頂点に向けて上昇する第1-12節には、絶対的で神聖なるものへの崇高な憧れに基づいて上方を目指す心の動きが、真昼を超えて暮れゆく時間にあたる第15-21節には、変化を拒み、融解する死者に同調し、永遠の停止状態の中に耽溺しようとする下降の感情がそれぞれ綴られている。そして、最後の第22-24節に至って、回帰する運動への準備として、詩人は下降する線上にあって力を漲らせ、吹き起こる風のエネルギーを得て再び上昇へと転じてゆくのである。vie/生きる詩人とabsolu/絶対者たる太陽、そして地中に眠るmort/死者というリヴによって厳密に支えられたこの構成は、生と死、運動と停止、身体と精神、一瞬と永遠といった複数の対立項を多層的に含みながらも生き生きとした運動を失うことはない。むしろ、ロマネスクからゴシック建築に至る構造的な改革によって壁面の軽量化がなされ、それに伴って施工可能となった大きなステンドグラスが教会の内部を美しい色彩に染め上げたように、詩句全体が交叉穹窿によって見事に浮遊するとき、その伽藍は途端に鮮やかな光に満たされるのである。
彼は、人間たちの移動する空間のなかに、明確な形態とほとんど音楽的な特性をくっきりと際立たせて光線を広げてゆく、比類のない装置を光線に対して用意したのです。さきほどあなたが考えた雄弁家や詩人たちと同じように、おお、ソクラテスよ、彼は、知覚できぬほどの抑揚のふしぎな力を知っていました。微妙にも軽やかに仕上げられ、しかも外見はきわめて単純な石材を前にして、感じ取れぬほどの曲線と、微細ながら全能の力をそなえた屈折とによって一種の幸福感へと導かれてゆく――[26]
厳密な建築的構成と生命の放縦な運動、その2つの極点を見事に結実させた構造物として、「海辺の墓地」はその内部に無限の運動エネルギーをほとばしらせ、何度でも我々に生きる試みへの意志を与え続けるのである。
(9270文字)
【引用】
[1] 長谷川富子『ヴァレリーの詩と建築:“海辺の墓地”をめぐって』大阪大学フランス語フランス文学会、1973年、64頁参照。
[2] ポール・ヴァレリー「海辺の墓地について」『ヴァレリー全集6:詩について』筑摩書房、1967年、242頁参照。
[3] 同上、249頁参照。
[4]中井久夫「ヴァレリー詩ノート」ポール・ヴァレリー著、中井久夫訳『若きパルク/魅惑』みすず書房、2003年、280頁参照。
[5] セット/Sèteの綴りは、1928年に変更されるまではCetteであった。
[6] ルイ・グロデッキ著、前川道郎・黒岩俊介訳『図説世界建築史8:ゴシック建築』本の友社、1997年、9頁参照。
[7] 長谷川富子『ヴァレリーの詩と建築:“海辺の墓地”をめぐって』大阪大学フランス語フランス文学会、1973年、63-85頁参照。
[8] 中井久夫「ヴァレリー詩ノート」ポール・ヴァレリー著、中井久夫訳『若きパルク/魅惑』みすず書房、2003年、284頁参照。
[9] 中井久夫「ヴァレリー詩ノート」ポール・ヴァレリー著、中井久夫訳『若きパルク/魅惑』みすず書房、2003年、284頁参照。
[10] 長谷川富子『ヴァレリーの詩と建築:“海辺の墓地”をめぐって』大阪大学フランス語フランス文学会、1973年、68頁参照。
[11] 中井久夫「ヴァレリー詩ノート」ポール・ヴァレリー著、中井久夫訳『若きパルク/魅惑』みすず書房、2003年、285頁参照。
[12] 長谷川富子『ヴァレリーの詩と建築:“海辺の墓地”をめぐって』大阪大学フランス語フランス文学会、1973年、69頁参照。
[13] 長谷川富子『ヴァレリーの詩と建築:“海辺の墓地”をめぐって』大阪大学フランス語フランス文学会、1973年、71頁参照。
[14] 天野利彦『「移行性」と「滞留」『海辺の墓地』に見るヴァレリー詩学の一面』静岡産業大学情報学部紀要、2007年、73頁参照。
[15] 中井久夫「ヴァレリー詩ノート」ポール・ヴァレリー著、中井久夫訳『若きパルク/魅惑』みすず書房、2003年、285頁参照。
[16] フョードル・ドストエフスキー『カラマーゾフの兄弟:中』新潮文庫、1978年、168頁参照。
[17] 長谷川富子『ヴァレリーの詩と建築:“海辺の墓地”をめぐって』大阪大学フランス語フランス文学会、1973年、73頁参照。
[18] アルベール・チボーデ著、森英樹訳『ポール・ヴァレリー』理想社、1970年、65頁参照。
[19] 同上、66頁参照。
[20] ポール・ヴァレリー「海辺の墓地について」『ヴァレリー全集6:詩について』筑摩書房、1967年、250頁参照。
[21] ポール・ヴァレリー『ヴァレリー全集:カイエ篇4』参照。
[22] 伊藤亜沙『ヴァレリーの芸術哲学、あるいは身体の解剖』水声社、2013年、149頁参照。
[23] 中井久夫「ヴァレリー詩ノート」ポール・ヴァレリー著、中井久夫訳『若きパルク/魅惑』みすず書房、2003年、286頁参照。
[24] 天野利彦『「移行性」と「滞留」『海辺の墓地』に見るヴァレリー詩学の一面』静岡産業大学情報学部紀要、2007年、72頁参照。
[25] 長谷川富子『ヴァレリーの詩と建築:“海辺の墓地”をめぐって』大阪大学フランス語フランス文学会、1973年、81頁参照。
[26] ポール・ヴァレリー著、清水徹訳『エウパリノス・魂と舞踏・樹についての対話』岩波書店、2008年、20頁参照。

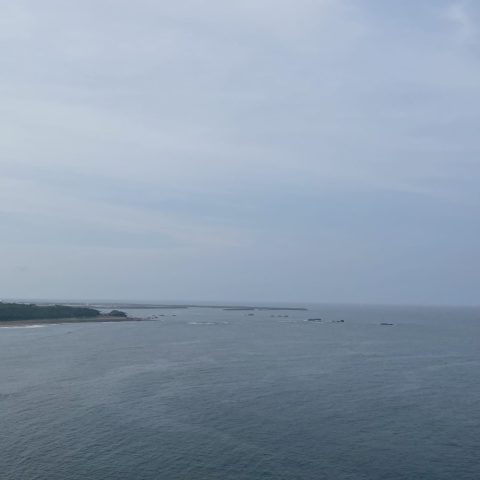
【今日の一曲】



