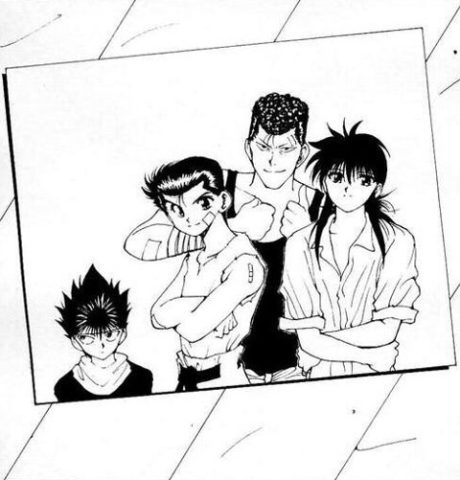これからPS2版「幽☆遊☆白書FOREVER」を持っている人同士で殴り合いをしてもらいます。
勝った方が勝者です。うゆです。
ようやく『幽☆遊☆白書』を読了、『ジョジョの奇妙な冒険』を6部まで読了&視聴したので、その感想を書きたいと思います。毎度のことながら長くなってしまったので、本記事では主に『幽☆遊☆白書』について言及します。ジョジョは気が向いたら次回。ほんじゃまた。
P.S.ホンジャマカは当初11人体制だったそうです。
「自称オタク」の泣きどころ〜幽遊白書、ジョジョを読んで〜
6年4組 うゆ
人と話しているとき、自分が今オタクを詐称したな、と思うことがままある。
サブカルチャーのことを大して知っているわけでもないのに、したり顔で自分のこだわりを開陳してしまう、あの瞬間だ。
ことにNewtypeでお給仕を始めてからはそれが多くなった。秋葉原という土地柄、いらっしゃるお嬢様ご主人様の中にもアニメや漫画、ゲームを愛好される方は多く、それだけオタク関連の話題にのぼる機会が増えるのも当然の話だろう。
残念なことに、実際のところ私はアニメも漫画もゲームもそれほど知っているわけではなく、したがって会話の内容がそうした類のサブカルチャーの事柄に定まってしまったとき、会話を満足に盛り上げることができないという大きな欠点を抱えている。「オタク」を自称して表向きはいっぱしのサブカル通ぶってはいるものの、その実『推しの子』も『フリーレン』も追えていない愚鈍なオールドファッションのコンコンチキに過ぎないのだ。
また、その欠点は海外のお嬢様ご主人様にご帰宅いただくことが多くなってさらに顕著になったとも思っている。海外旅行の行き先として日本を選び、さらにわざわざ秋葉原で降りてみようなんてことを考える人は大抵の場合日本のサブカルが好きなのだ、“What brings you to Japan?”と尋ねると多くの人は”Japanese animation.”と答える。さらにそこでお気に入りのタイトルなんて不用意に聞いてしまおうものなら一巻の終わりである。相手の口から飛び出す数々の正体不明のアニメタイトルの数々。名前は聞いたことありますねなんて誤魔化してはいるが内心冷や汗ものだ。一体この会話をどうやって盛り上げたらいいんだ?脳内ではルフィやら孫悟空やらが肩を組んで蛍の光を大合唱している。止まらない冷や汗、聞き取れない外国語。
さて、そんな重大な欠点を抱えた私にとって、特に泣きどころと言うべきタイトルがふたつ存在した。これはメイドとしてというのに限らず、日常生活においても当てはまる、自称オタクのくせにまだ視聴すらしていないことを恥じるべき二大タイトルだ。
そのふたつというのがずばり冨樫義博の『幽☆遊☆白書』と荒木飛呂彦の『ジョジョの奇妙な冒険』。両者はかなり昔からあるジャンプ系の王道タイトルで、連載開始から何十年もたった今でも多くの人々に語り継がれている名作である。その影響力は特にインターネットミームのかたちに強く現れていて、「右ストレートでぶっ飛ばす」や「だが断る」などのセリフをSNSなどで見たことのある人も少なくないだろう。ミームというのは不特定多数の人に自然と共有されたお決まりの冗談みたいなもので、人はミームの内容そのものというより、「お決まり」であるというコンテクストを含めてそれを楽しむ傾向がある。したがって、アニメや漫画、ゲームの一場面がミーム化するためには、まず作品がそれだけ多くの人の目に触れ、さらに単なる一場面にすぎないはずのものが、作品本体から切り離されてなおキャッチーさとインパクトを持ちえている必要があるといえる。『幽☆遊☆白書』や『ジョジョ』がそれだけ多くのミームを未だに世間に残しているということは、両者がやはり圧倒的な魅力と強烈な個性を持ち合わせているということを意味するのだ。
しかし、恥ずかしいことに私はこれまでそのどちらも読んで(あるいは観て)はいなかった。これといった理由はない。単に気が進まなかったのだ。両者の内容は連載時期ゆえにどうしても今の漫画に比べてベタである感が拭えないし、絵柄が古かったり巻数が多かったりするせいであまり読もうという気が起きないというのが正直なところだった。後世になってシェイクスピアの劇につまらないとクレームを入れたおばさんと同じである。
「あんなのどれもこれも見たことのある展開ばっかり!盗作じゃないの!?」
逆である。シェイクスピアの考えた展開が後になって多くの作品に取り入れられたのだ。それが何度も何度も使い回され、クリシェとなって古ぼけていくうちに、人々の作品を見る眼はどんどん肥えていって、元になった作品をつまらなく感じてしまうのだ。古典的名作の悲しき性と言うべきかな、『市民ケーン』も『サイコ』も、あるいは『オデュッセイア』も『ボヴァリー夫人』もみな同じような末路を辿っている。いまさらこれらの作品を喜んで見ようというような人は相当な暇人か、あまりにも現代の娯楽を知らない不幸な人だろう。
古典を楽しめないのは仕方のないことだ。そもそも芸術の刷新とは古典への飽きと抵抗から生まれる。それは正常どころか必要な作用なのだ。しかし、私の場合はもう少し傲慢である。『幽☆遊☆白書』や『ジョジョ』を古典、つまらないと言って敬遠してながら、そのくせミームの恩恵には与ろうとし、あまつさえサブカル通ぶった顔で不遜に威張り散らしてみせたりもするのだ。私が漫画通を気取って色々と喋り散らかした末に『幽☆遊☆白書』も『ジョジョ』も読んでいないと知ったときの相手の表情たるや!箸も持てないのに日本人を名乗っているの?駿台模試も受けないのに受験生を名乗っているの?そういうときと同じ、失望と、嘲笑と、疑いとが混じったあのえもいわれぬ曇った表情である。私はそろそろ耐えられなくなってしまった。あの表情と、なにより自分自身の内に秘めた大きな欺瞞にである。
朝露の名残が空気中に漂って微細に輝く冬晴れの美しい一日。私は意を決して『幽☆遊☆白書』のコミックを購入、その勢いのまま読みふけった。
“baby steps to giant strides!!“
きっかけなんてなくてもいい。始めることが重要なのだ。
ここでCM。
4/29(火)はめいの生誕イヴェント!!
テーマはアリス。めいがNewtypeにスコップで大きな穴を掘って埋め、また掘って埋めを繰り返し続けます。
汗だく、泥だらけのめいを見ながら飲むお酒はさぞ美味いことでしょう。
超面白い盛り上げ上手のめいと一緒に楽しみましょう。

序盤はめちゃくちゃつまらなかった。やっぱりダメだった。
…この時点でどうか怒らないでいただきたい。私のことを感性の死んでなおつらつらと駄文を書き連ねる文豪気取りの言葉ゾンビだなんて思わないで、どうかもう少しお付き合いされたし。
序盤という病。主人公・浦飯幽助が不良っぽいのに時代を感じる。そして彼が実は義理堅く弱い者に優しいというのもよくあるパターン。トラックに轢かれかけていた幼児を庇って死んだ主人公、しかしエンマ大王すら予期していなかったその行動に霊界はおおわらわ。本来死ぬ予定でなかった浦飯は、人間界と霊界の狭間で様々な魂絡みの事件を解決する「霊界探偵」として徳を積み、復活の刻を待つのである。この時点では「蔵馬は?飛影は?」という感想で、噂に聞いていた方向性とひと味違う展開に果たしてこれが本当に『幽☆遊☆白書』なのだろうかと首を傾げる始末。面白くなくはないがおしなべて地味でシンプルな起承転結にあくびをかみ殺す。
そして4巻くらいからようやく噂の蔵馬や飛影といった人気キャラが登場する。はじめは霊界探偵が処理すべき敵として登場するのだが、その中に秘められた一貫した強い目的意識は、やがて浦飯との共同戦線へと彼らを向かわせてゆく。この顛末は面白かった。これがあったからなんとか読み続けることができたと言っても過言ではない。
ただし朱雀編、テメーはダメだ。(一応ことわっておくが、私はボーボボを読んでいない)
『HUNTER × HUNTER』を愛読する中でよく了解している通り、冨樫先生は絵はもちろんのこと、なにより表現がうまい。コマ割りやタッチの軽妙な緩急で物語にダイナミズムとインパクトを与え、ときに文字数が少年漫画の閾値を大きく外れていてもそこに作品の生き生きとした呼吸を生み出す。メルエムとコムギのシーンや、シャウアプフの恐ろしい表情など、非音声表現の中にも確かな沈黙と破断の息を呑むような緊張感が浮き彫りになっている。読者の呼吸を作品に同期させたうえで自在にコントロールする技量は圧巻の一言だ。しかし、『幽☆遊☆白書』の初期には背景のシンプルなコマが多く、またタッチが微妙に違っているせいで登場人物の動きがかたく感じてしまう。それに、魔物というのもあってか相手キャラについての掘り下げがほとんど全く行われないので、ぽっと出のよく分からない気持ちの悪い生き物が主人公たちにベルトコンベア式に倒されていくという印象をどうしても抱いてしまうというのが正直なところだ。『HUNTER × HUNTER』ではどう見ても噛ませキャラでしかないビノールトにさえ過去編が描かれていたことを考えると大きな差だ。敵の素性を隠すためにあえて、というのではなく本当によく分からないので、その辺りの展開は本当につまらなかった。
続く暗黒武術会編。霊界の任務中にとある闇のブローカーと出会ってしまった飛影、蔵馬、浦飯の3人は、彼が魔界で主催する暗黒武術会という大会に強制的に参加させられることになる。修行の中で霊力の才能を開花させた浦飯のライバル・桑原も加えて恐るべき大会を勝ち進んでいく。果たして最強の敵・戸愚呂兄弟を倒すことはできるのか。
意外に思われるかもしれないが、これもあまり面白くなかった。原因はやはり敵についての掘り下げが行われないことで、総じて単調に感じてしまった。ただ、朱雀編と違って魅力のある敵キャラが増えてきたのと、主人公一行の能力が向上してきたことで、つまらないというほどではなかった。飛影の「炎殺黒龍波」はとても良かった。でもDr.イチガキという名前はなんとかした方がいいと思う。個人的に本作の面白さはこの辺りから少しづつギアが上がってくる。ただ悲しいかな、この時点で全19巻のうちの13巻である。
暗黒武術会編が終わってすぐに始まるのが仙水忍編だ。ここを境に本作は純粋な霊力の殴り合いバトルから『HUNTER × HUNTER』の念能力のようなテクニックバトルの趣を多少帯びるようになる。漫画のバトルシーンが何より嫌いな私にとっては、つまりここからが本作の美味しい部分ということになる。修行によって霊力の新しい使い方を覚えた浦飯たちは、人間界と魔界とを繋げようと目論む仙水忍一行の恐るべき計画に挑む。仙水の圧倒的な実力に片膝をつく浦飯、彼以外に誰が仙水を止められるというのだろう。人間界に危機が迫る─。
ここは非常に面白かった。能力バトルになるため、さほど武力のないキャラクターにもチャンスが与えられるし(特に天沼とのゲーム対決で海藤が活躍するのがいい)、なによりこの辺りの冨樫先生の画力が異常なので、紙面から伝わってくる限りない臨場感に期待が止まらなくなる。また、仙水忍というキャラの掘り下げが大変魅力的だった。人間への憎悪と愛の狭間で引き裂かれてしまった非業の天才…。仙水は私が幽遊白書で一番好きなキャラクターだ。こころなしか『寄生獣』の後藤とイメージがかぶる気がする。
読了した今の感想として、私の中で『幽遊白書』は非常に面白かった作品として記憶に残っている。もちろん、13巻までの物足りなさを含めた上でだ。それにはやはりこの仙水忍編が純粋に楽しめたことがあって、それに加えて本作のラストをかざる魔界統一トーナメント戦もまたかなりの傑作だったことが大きく影響している。
魔界統一トーナメント編のあらすじには重大なネタバレが含まれるためあまり触れられないが、とにかく読んで字のごとく、今まで出てきた魅力的なキャラクターや、それを遥かに凌駕する実力を持った数々の猛者たちが、魔界全体の王の座をかけてトーナメント戦をおこなうという内容だ。このトーナメントには参加者が何千人といて、作中でフィーチャー(全く関係ないが、feature/注目して取りあげるをfutureと勘違いしている人が多い。フューチャーは、未来である。)される本戦出場者だけでも100人以上存在する。したがって、このトーナメントが作中で最後まで描かれることはない。結果は判明するが、過程はほとんどが省略されている。ただ、私はそのことがなにより気に入っている。内容を冗長に引き伸ばさず必要で面白い部分だけ潔く切り上げるというやり方は漫画が良作であるために不可欠な要素だと思うからだ。それをしたから『SLAM DUNK』は名作で、しなかったからジョジョ3部の前半や『弱虫ペダル』の2年目以降、『HUNTER × HUNTER』の暗黒大陸編(なぜ冨樫は同じことをもう一度できなかったのだろう?)はダレているのである。『幽遊白書』は一見あっけないような結末でフィナーレを迎え、最終コマの桑原の謎ポーズだけが一部でいじられることになっているが、それでもひとつの物語の区切りのつけ方として非常に素晴らしかったと思うし、だからこそ本作が長い年月を経てなお名作と目されているのだ。
以上のように、『幽☆遊☆白書』は素晴らしい作品であり、私はこのため息の出るような深い満足感とともに、自称オタクとしての2つの弱点のうちひとつを克服したのだった。古い作品だからと、序盤が絶望的におもんないからと敬遠しているあなたも、ちょっとづつの勇気とモチベーションだけで素晴らしい読書体験が味わえることだろう。ぜひ、本棚の隅からその日焼けした往年の背表紙を見つけ、しばしの間優しく寄り添ってみてはいかがだろうか。