うゆです。
「バニラ求人」のアドトラの運転中に大事故を起こして死刑判決を受けたことがあります。(しかも2回)
明けましておめでとうございます。
1月中に観た映画31作品をまとめました。
毎日一作のペース、と言いたいところなのですが、一応ショートフィルムも3作含まれているのでべつにそんなことはありません。
1月は「今年ログインボーナス」と称してカンヌ受賞作をふんだんに鑑賞したので当然当たり作品がめちゃくちゃ多く、類を見ないほど幸せな一ヶ月になりました。
毎回特に良かった10%の作品をフィーチャーして紹介しているのですが、今回はあまりにもいい作品が多く決めきれないため、紹介できるだけしようと思います。基準としては、大変無粋で申し訳ないのですが、映画批評サイトで自分が4.5/5点以上をつけた作品とします。だいたいそれが今まで観てきた作品のうち上位10%にあたるからです。映画に数字をつけるのは野暮だとは重々承知ですが、恐らく最後の映画ブログになると思うのでできるだけたくさん紹介したいのです。
以下、一覧です。
1.『コンパートメント no.6』ユホ・クオスマネン
2.『ルノワール』早川千絵
3.『ヤンヤン:夏の思い出/Yi Yi: a one and a two』 楊 德昌
4.『訪問、あるいは記憶、そして告白』マノエル・ド・オリヴェイラ
5.『カニヴァイシュ』マノエル・ド・オリヴェイラ
6.『ザ・ザ・コルダのフェニキア計画』ウェス・アンダーソン
7.『アバター:ファイヤーアンドアッシュ』ジェームズ・キャメロン
8.『アブラハム渓谷』マノエル・ド・オリヴェイラ
9.『枯れ葉』アキ・カウリスマキ
10.『KES』ケン・ローチ
11.『家族を想うとき/Sorry we missed you』ケン・ローチ
12.『わたしは、ダニエル・ブレイク/I, Daniel Blake』ケン・ローチ
13.『街をぶっとばせ』シャンタル・アケルマン(ショートフィルム)
14.『男女残酷物語:サソリ決戦』ピエロ・スキヴァザッパ
15.『恋する惑星/重慶森林』王家衛
16.『悪魔のいけにえ 公開50周年版』トビー・フーパー
17.『ミレニアム・マンボ』侯孝賢
18.『ブレア・ウィッチ・プロジェクト』複数人
19.『動くな、死ね、甦れ!』ヴィターリー・カネフスキー
20.『ひとりで生きる』ヴィターリー・カネフスキー
21.『ロゼッタ』ダルデンヌ兄弟
22.『バグダッド・カフェ』パーシー・アドロン
23.『レイブンズ』マーク・ギル
24.『SOMEWHERE』ソフィア・コッポラ
25.『コロッサル・ユース』ペドロ・コスタ
26.『ホース・マネー』ペドロ・コスタ
27.『わたしたちの男』ペドロ・コスタ(ショートフィルム)
28.『溶岩の家』ペドロ・コスタ
29.『ヴィタリナ』ペドロ・コスタ
30.『火の娘たち』ペドロ・コスタ(ショートフィルム)
31.『処女の泉』イングマール・ベルイマン
良かった作品(順不同)
1.『わたしは、ダニエル・ブレイク』

ケン・ローチ、2016年、ベルギー・イギリス・フランス、100分。
鑑賞方法…U-NEXT
イギリスが生んだリアリズムの秀才による渾身の一作。勝手に始めた「自主ケン・ローチ特集上映」の3作目として視聴したが、前の2作があまりに救いがなかったため、本作も覚悟のうえで挑んだ。
心臓病により医師に休職を命じられるも、失業保険の手続きを巡る役所の冷酷で矛盾した対応に徐々に疲弊していく大工の老人ダニエル・ブレイク。ひょんなきっかけで出会ったシングルマザーのケイティやその子供たちと不器用ながらも家族のように暖かい絆を育んでいくが、貧困の影は彼らを容赦なく蝕み、嘲笑うように広がっていく。
物語というものの威力を直に食らった作品。ケン・ローチはショットでなくシーンで魅せる。カットの間が短いのでテンポが良く、物語に一気に引き込まれてしまう。
監督自身が問題意識として抱く現実のイギリス社会における社会保障制度への疑念に立脚しており、可視化されづらいデジタルディバイドや差別の実態が克明に描かれている。特に、子どもたちのために何日も食べ物を口にできなかったケイティが、配給所で人目もはばからずパスタソースを啜りだすシーンには圧倒された。彼女は惨めに泣き出し、その様子を子どもが怯えたように見つめている。善良な人の尊厳をいとも簡単に食い殺してしまう貧しさという病と、それに見て見ぬふりを決め込むシステムに強い怒りが込み上げ、続いてやるせなさに胸がいっぱいになる。『家族を想うとき』も素晴らしい作品だったが、本作の方が終わり方にまだ救いがあるのでこちらを選びたかった。観やすさ、おすすめのしやすさ、という点においては今回のブログでは一番だと思います。



2.『アブラハム渓谷』
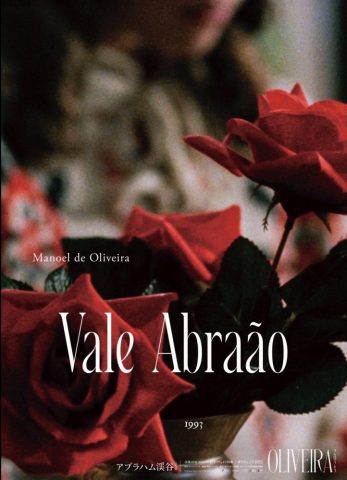
マノエル・ド・オリヴェイラ、1993年、フランス・ポルトガル・スイス、205分。
鑑賞方法…早稲田松竹
フローベール『ボヴァリー夫人』の翻案として、ポルトガル国内のとある渓谷を舞台に、愛と喪失に冷たく燃える女の生涯を大河的に描ききった大作。愛に溺れるファム・ファタール、エマの恐るべき美貌は、決して満たされない愛欲への欠乏と一体になって彼女の苦悩にいっそう深い陰影を刻んでいる。
205分、休憩なしでの耐久。辛いかと思えばそうでもなかった。きっと前日に見たアバター(192分)のおかげだろう。わたしは死ぬほど多動なうえ200分ずっとパッケージをパリパリさせながらポップコーンを啄み続けていたので隣の人にはさぞいい迷惑だったろう。(伊丹十三の映画の冒頭に、劇場で袋をパリパリさせながらお菓子を食べている男にブチギレるシーンがある)
うんざりするほど長いが、これは時間芸術である映画として、ひとつの生の存在を観客の眼前に生々しく立ち上げるために必要な尺であると思う。各所に挟まれるアブラハム渓谷の静寂。ドウロ川の水面は完全に停止しているように見えて実は絶え間なくせせらいでいる。砕け散る白光の一つ一つはそのまま数限りない人の存在と歴史を示しているようだ。生の密度は雄大な風景と対比されてあまりに重く苦しい。
ドビュッシー「月の光」を劇伴として、ロウソクの幽かな灯りをたよりに夫の寝室へ赴くエマを長回しで映したショットには鳥肌が止まらなかった。燃え立つ光に応えるように影も燃えていた。霊的なものの底知れない暗い決意を滲ませたエマの表情を忘れることができない。



3.『コンパートメント no.6』

ユホ・クオスマネン、2021年、ロシア・エストニア・ドイツ・フィンランド、107分。
鑑賞方法…U-NEXT
ペトログリフ(岩面彫刻)をひと目見るために、考古学徒のラウラはひとりシベリア鉄道に乗って極北のムルマンスクまでの旅に出た。恋人との不和。ロシアの寒風が剥き出しになった別離の傷を鋭く痛ませる。全てが等しく死んだように白い冬景色が、吹きすさぶ雪に紛れて窓外に流れていく。
立て続けに襲い来る不幸と不運に人生のどん詰まりを予感する女性と、図らずもその旅の道連れとなってしまった同室の青年との交流を描いた作品。飲んだくれて執拗に絡み、ときに下品な言葉を浴びせる青年にはじめは辟易とする彼女だったが、孤独の中でその不器用な気遣いを受け入れていく。
寂寥感に満ちたシベリア鉄道沿いの風景にひときわ痛々しく浮かび上がる孤独の存在がスクリーン越しに観客の心を蝕んでくる。カメラは登場人物への不安定な接写を繰り返し未来も過去も映し出してはくれない。コンパートメント内や寒村のざらついた照明はラウラの投げやりな失望を示すようでもある。寂しさの中にゆっくりと浮かび上がってくる”travelhood”は恋とも友情とも少し違って、ずっと曖昧で寄る辺ない愛情の接近にすぎないのかもしれない。



4.『枯れ葉』

アキ・カウリスマキ、2023年、フィンランド・ドイツ、87分。
鑑賞方法…U-NEXT
つまらない理由で仕事をクビになった中年女性アンサと、アル中の中年男性ホラッパのささやかな出会いとすれ違いが、アキ・カウリスマキ独自のペーソス溢れるスタイルで描かれる。
尺は81分と短く、ストーリーも非常にミニマムでありながらどうしても心に焼き付いて離れない瞬間がある。貧困の中で弱さをもてあまし、愛情の向け方さえ分からないまましかめ面で生きる人々。弱さの中に、それでもなお息づいている善性が強く胸を打ってくる。抑制された語りはカウリスマキのユーモアに彩られてどこか微笑ましくもあり、彼らの横顔は初冬の澄んだ陽にあてられて険しいのに柔らかい。
陽だまりの中のラジオが惨劇を伝え続ける。
疲れて棒切れのようになった脚を犬がくるみこむ。
誰でもいいからとにかく大好きな人たちに大好きだと伝えずにはいられなくなるような気持ちが湧いてくる。映画を好きな理由が詰まった一作。



5.『動くな、死ね、甦れ!』
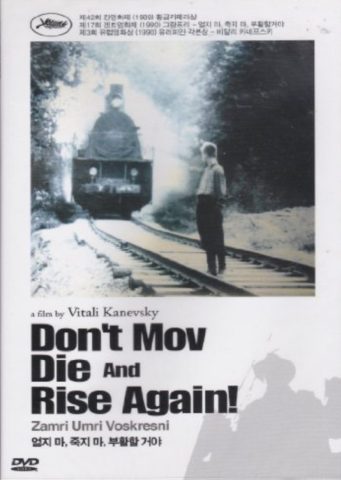
ヴィターリー・カネフスキー、1989年、ロシア、105分。
鑑賞方法…Morc阿佐ヶ谷
かつて早稲田松竹ではじめて観た作品。今回は前回登場人物の顔を見分けられなかった反省を活かして再挑戦。
戦後すぐのソヴィエト極東にある炭鉱町。12歳の少年ワレルカは大人たちにイタズラをしかけて騒動を巻き起こすのだが、そのたびに幼なじみの少女ガリーヤが守護天使のように彼の危機を救ってくれるのだった。しかし、とうとう学校を退学になってしまったワレルカの腹立ち紛れのイタズラが大惨事を巻き起こし、遠く祖母の家へ逃避行へ出たことを境に、2人の運命の歯車は大きく狂いだしていく。
おそらくトリュフォーの『大人は判ってくれない』に影響を受けたのであろう作品で、本作にもまた成長過程の少年と社会との軋轢、そして絶望的な結末までが描かれている。カラー映画時代の作品であるにも関わらず白黒なのは予算不足ゆえだと言うが、本作の場合はそれがむしろロシアの冬景色の空白と、雪に乱反射してオーバーフローする光の幻想的なイメージを強めていたように思う。非行少年時代を生きたカネフスキー監督自身のノスタルジアが重ねられた少年ワレルカ。その目で捉えられた戦後ロシアの姿は美しくも厳しく死と痛みの匂いに満ちている。シベリアに抑留された日本兵たちが歌う炭坑節、片足の兵士たちのダンス、白銀の朝に燃え盛るリンチ死体。
ラストシーンは映画史に残るほどの衝撃をもって身を貫いてくる。共感はもはや意味をなさない。カネフスキーのデビュー作でありながら圧倒的な完成度で、編集から撮影までが鬼気迫るクオリティで仕上げられている。



6.『ひとりで生きる』
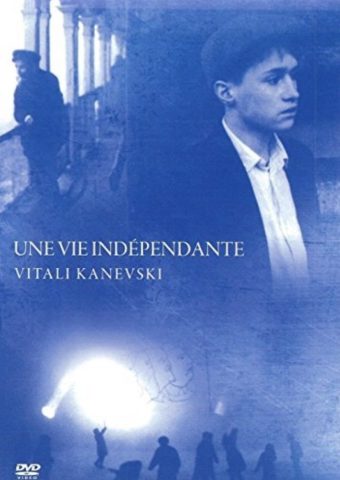
ヴィターリー・カネフスキー、1991年、ロシア、97分。
鑑賞方法…Morc阿佐ヶ谷
『動くな、死ね、甦れ!』に続けて鑑賞。前作の衝撃をまだ引きずっていたうえ、後ろの席の人が私の座席の背もたれでリフティングをしていたので上手く集中できなかったが、それでも本当に素晴らしい作品だったと言える。
『動くな、死ね、甦れ!』の続編として、青年になったワレルカに再びカメラが向く。ガリーヤを亡くしたワレルカには、今やガリーヤの妹であるソーニャが次の守護天使として付き添っていた。今度は青年として世界に立ち向かい、理不尽に打ちひしがれて絶望を知ったワレルカは街を離れ、ひとりで生き抜いていくことを決める。
一作目の成功で予算がおりたようで今度はきちんとカラーになっており、前作独特のコントラストは失われてしまったものの、ものや光の表情はより豊かに捉えられるようになった。物語は非常に難解だが、ショットがバチバチにキマっており、瞬間ごとに炸裂する印象は実に鮮烈である。ワレルカはやはりカネフスキー自身の幻影として、映画という装置を強烈に意識しているように思える。魂をそのままちぎりとって差し出すような強烈な独白と沈黙、波間に消え去っていく語り部。爆裂する巣から散り散りに駆け出していく火だるまのネズミ、棺からムックリ身を起こす死者。物語の内外はぼやけ、語り手の語り手としての自我の獲得とともに生と死、現在と過去すらもが曖昧になっていく。



7.『溶岩の家』

ぺドロ・コスタ、1994年、ポルトガル・フランス・ドイツ、110分。
鑑賞方法…目黒シネマ
12月にTOPで開かれた「インナーヴィジョンズ」での特集上映で見逃していた、初期三部作の二作目。
現場作業中の事故で重症を負った作業員を故郷カーボベルデへ送り届けることになった看護師のマリアーナ。病人とともに現地へ滞在するうちに、人々の温存する狂気や死の気配に出会う。
かつてポルトガルの植民地として海上拠点の要所となった火山島カーボベルデ。無垢な空を貫くようにそびえる火山を楽園のように頂いて、地表は多孔質の黒土に覆われて作物ひとつ育たない不毛の地である。飢餓があり、祝祭があり、漣があり、生と死がある。ペドロ・コスタは本作以降一貫してカーボベルデ移民を始めとするポルトガルの貧困の姿をカメラに収めようと奔走するが、本作はその先駆けとして、まず監督自身がカーボベルデの地に踏み込んでいく。
右方向に移動し続けるだけの長回しや家屋のショットなど、一作目『血』でブレッソンや溝口の影響を多大に受けたシネフィル青年が、自分の本当に撮るべきものを明確に掴みえたのだとわかる瞬間があった。1人の映画監督が誕生する瞬間を目撃する感慨に胸がいっぱいになった。



8.『ホース・マネー』

ペドロ・コスタ、2014年、ポルトガル、104分。
鑑賞方法…目黒シネマ
『コロッサル・ユース』(2006)と『ヴィタリナ』(2019)とだいたい同じなので、それらも合わせて本作を紹介する。
『ヴァンダの部屋』以降、ドキュメンタリーとフィクションの際を探る映画を求め続けてきた監督がひとつの到達点として完成させた作品。前作『コロッサル・ユース』に引き続き、カーボベルデ移民の一般労働者であるヴェントゥーラを本人役の俳優として起用、その質朴な存在感はスクリーンの枠をすら揺るがせて映画を映画以上の生の体験へと高めている。
1974年4月25日のポルトガルで発生した軍事クーデターは「カーネーション革命」と呼ばれ、ヨーロッパ最長の独裁政権「エスタド・ノヴォ」をほとんど無血に終わらせた市民の華々しい成果として知られている。しかし、その裏にはそもそも市民として顧みられることのなかったカーボベルデ移民たちの犠牲があった。1974年4月25日で記憶を停止させたヴェントゥーラは、廃墟のようになった精神病院を亡霊のように歩き回りながら、そぞろな回想の中に身を投じる。映画は彼の魂を追跡するように時間から離れて過去の暗闇の中を飛び回る。
『ヴァンダの部屋』、『コロッサル・ユース』、『ヴィタリナ』と同様、照明機材を使わず全て自然光のみで撮影された画面は常に薄暗く、幽く部屋を明るませる午後の光や闇に差し込む一条の光はもはや世界を照らす意思をなくしてしまったようにも見える。ヴェントゥーラの黒い肌は暗闇の中に溶けてむしろ死者のそれに近く、消極的な光に身体のどこかをなおざりに明るませて闇よりもいっそう濃密に闇を縁どっている。
終盤には監督がアキ・カウリスマキ、ヴィクトル・エリセ、マノエル・ド・オリヴェイラらと発足させたオムニバス・プロジェクトにおいて発表した中編『スウィート・エクソシスト』(2012)が、多少の再編成を行ったのみで丸々挿入され、本作に圧倒的な重量を加えている。
暗く重い油のようにドロリと流れ出してくる記憶の暗部。トラウマの再演。ヴェントゥーラは普遍的な物語の代弁者ではなく実に個人的な体験者に過ぎない。しかし、だからこそ彼の語りは湿った土、剥がれたコンクリート、むき出しになったレンガ材の内側に染み込んだ証言として鋼のような密度を持つのである。




以上になります。この他にも本当は『ヤンヤン 夏の思い出』や『ルノワール』、『家族を想うとき』、『街をぶっ飛ばせ』、『ロゼッタ』、『ミレニアム・マンボ』、『処女の泉』などの作品も大変素晴らしく、本当なら紹介させていただきたかったのですが、尺の都合上今回はここで終わりにします。(「フェルマーの最終定理」みたいでかっこいいでしょ)
これでうゆからの映画紹介ブログは多分最後になります。長いことどうもありがとうございました。
【今日の一曲】
「Romanzo」エンニオ・モリコーネ
ベルナルド・ベルトルッチ監督『Novecento』のサントラで、全ての映画音楽の中で一番好きな曲です。






